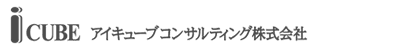![]()
業務単位分析によるコスト削減事例
S消費者信用会社における無担保個人ローンの保証業務例
<背景>
S消費者金融会社においては、地域金融の低迷化、大手消費者金融との競争激化などにより業績拡大が難しくなっていました。そのような中、業務多角化の一環として上記「無担保個人ローンの保証業務」を開始しました。 当初の業務計画では、無担保個人ローンは本業でありノウハウも十分あること、システムも本業の流用が可能と考えられたことから本保証業務も十分収益が得られるものと考えられていました。
保証業務は、銀行の上限金利である18%の半分に当たる9%を収入源として業務計画が立てられていました。 しかし、本業は貸出金利が当時29.2%に対し総コストは13%強で運用されており、それをベースとした業務体制で本業務の運用を開始したため、殆ど残高も無く収益も当然赤字でした。
本業務を収益の一つの柱とするため、新たに担当の役員が選任され、担当役員から筆者もプロジェクト・マネージャーに選任されました。
S消費者金融会社においては、地域金融の低迷化、大手消費者金融との競争激化などにより業績拡大が難しくなっていました。そのような中、業務多角化の一環として上記「無担保個人ローンの保証業務」を開始しました。 当初の業務計画では、無担保個人ローンは本業でありノウハウも十分あること、システムも本業の流用が可能と考えられたことから本保証業務も十分収益が得られるものと考えられていました。
保証業務は、銀行の上限金利である18%の半分に当たる9%を収入源として業務計画が立てられていました。 しかし、本業は貸出金利が当時29.2%に対し総コストは13%強で運用されており、それをベースとした業務体制で本業務の運用を開始したため、殆ど残高も無く収益も当然赤字でした。
本業務を収益の一つの柱とするため、新たに担当の役員が選任され、担当役員から筆者もプロジェクト・マネージャーに選任されました。
1.ビジョンを設定する
担当の役員は中期事業計画の中で「統合コストを残高の6%とし利益は3%、3年後に残高1000億円にする」という高い業務目標を役員会で公約(Commitment)しました。
この中期事業計画に基づき営業を含む人員計画が策定され、早期の業務システムの新規構築が求められました。
2.プロジェクトの体制:実行リーダーと担当者を決める
本プロジェクトは対象業務が広く、始めから最終責任者は担当の役員であり、実行リーダーは筆者(部長)が担当しました。筆者は、経営陣に対して業務システム構築だけでなくシステムプロジェクト遂行上の問題と対応策についての説明責任が求められたため、どのような方法で本プロジェクトを推進すべきか悩み、結局、経験と実績のある業務単位分析によるアプローチ方法にたどり着きました。
サブリーダーには経験豊富なシステム担当課長をアサインして外部コンサルタントの役目を筆者が担当しました。 プロジェクト参加者は保証業務部門の各業務担当者とシステム部門の担当者とし、システム開発・運用者であるメーカー担当者も入れて総勢20名程度のチームを構成しました 。
サブリーダーには経験豊富なシステム担当課長をアサインして外部コンサルタントの役目を筆者が担当しました。 プロジェクト参加者は保証業務部門の各業務担当者とシステム部門の担当者とし、システム開発・運用者であるメーカー担当者も入れて総勢20名程度のチームを構成しました 。
3.現状業務の把握をする
本来本業である無担保個人ローンの貸出残高に対する総コスト率が13%強であるビジネスモデルを基に、総コスト率を6%に変えるモデルを構築することは、当初から相当大変なプロジェクトであると想像されました。
そのため、まず始めに、関連する既存の本業の業務フローを作成し、業務分析を行い、各部門の管理会計・実績情報から重点的に効率UPすべき業務部分を特定して、既存の保証業務に業務フローを引きなおして現状分析しました。
現状分析には、プロジェクトメンバー全員の3回の合宿と一月強の期間が必要とされました。
また、提携銀行獲得のためには各銀行の細かい要求に柔軟に対処すべきとの判断から、銀行毎のパラメータ設定により容易に条件変更ができるように仕様を決定しました。
また、提携銀行獲得のためには各銀行の細かい要求に柔軟に対処すべきとの判断から、銀行毎のパラメータ設定により容易に条件変更ができるように仕様を決定しました。
| 例 | A銀行 | B銀行 | C銀行 |
|---|---|---|---|
| 融資対象者 | 収入がある方 | 満20歳〜65歳未満 | 満20歳以上 |
| 融資限度額 | 300万円 (初回100万) |
10万〜100万円 |
10万〜50万円 (10万単位) |
| 融資利率 | 9.0%〜18.0% | 14.0%〜17.0% | 9.8%〜18.0% |
| 返済方式 | 返済日35日サイクル | 毎月7日 | 毎月指定日 |
このような検討過程において、業務遂行上の問題点が明らかになり、具体的な業務処理手順とシステム対応の改善策がイメージできました。 システム対応は、無担保個人ローン保証業務処理はホストコンピュータによる本業システム機能をほとんど流用して開発されていたため、基幹業務処理部分だけを残して、保証の主要業務である受付・審査の業務と業務効率を徹底的に追求したマンマシン・インターフェイスを構築するサーバークライアント構成とすることにしました。
4.業務プロセスの変革を決定する
現状業務の把握のため、関連する本業の業務フロー分析と業務分析を行いました。
既存の保証業務の業務フローを作ったことで効率UPすべき受付・審査の業務が特定でき、それら業務は、中期事業計画では人員が徐々に増加する計画であり人件費が大きなコスト要因であることから、保証の主要業務である受付・審査業務の効率を徹底的に追求した業務フローを構築しました。
また、システム構成が固まったことから、中期事業計画に基づき月間の統計情報を想定したシステム規模の策定と目標とすべき業績管理方法の策定を行い、銀行との顧客情報交換の迅速性確保と提携銀行支援のためのWeb申し込み受付代行機能の提供を策定しました。
具体的な業務フロー変革の検討では、効率化の効果が出やすい受付・審査業務に特化し、詳細に業務とシステム機能の原単位に分類し業務効率が達成できるように業務フローを再構築しました。
また、受付・審査業務は徹底的に自動化とパラメータ化を追求したものにしました。同時に、マンマシン・インターフェイスは効率と正確性を重視して業務フローに応じて表示される個人情報入力画面、進捗情報画面、判断・承認画面などを設計しました。
また、システム構成が固まったことから、中期事業計画に基づき月間の統計情報を想定したシステム規模の策定と目標とすべき業績管理方法の策定を行い、銀行との顧客情報交換の迅速性確保と提携銀行支援のためのWeb申し込み受付代行機能の提供を策定しました。
具体的な業務フロー変革の検討では、効率化の効果が出やすい受付・審査業務に特化し、詳細に業務とシステム機能の原単位に分類し業務効率が達成できるように業務フローを再構築しました。
また、受付・審査業務は徹底的に自動化とパラメータ化を追求したものにしました。同時に、マンマシン・インターフェイスは効率と正確性を重視して業務フローに応じて表示される個人情報入力画面、進捗情報画面、判断・承認画面などを設計しました。
5.同時並行して業務運用上の問題の分類と対応策を検討する
問題は、1)人事・組織的問題、2)業務上の問題、3)個別能力に分類することとしました。
特に業務フローをシンプルにするために考慮した点は、1)、2)の問題でありアルバイト社員が多いことから、人事上の判断・承認権限の無い場合が想定されました。
結果、あくまでも業務効率を優先させたため、一部アルバイトの職務権限を上位者として扱えるように人事的な対応を取ってもらいました。
2)、3)の問題では、アルバイトのやる気の問題がもっとも重要な問題と認識した結果、システムテストからリーダーを決め、時給にも配慮することでシステム立ち上げ時からスムーズに移行できました。
2)、3)の問題では、アルバイトのやる気の問題がもっとも重要な問題と認識した結果、システムテストからリーダーを決め、時給にも配慮することでシステム立ち上げ時からスムーズに移行できました。
6.効果を把握して、継続的に変革を繰り返す
新システム移行後は、システム部門のプロジェクト参加者が常時現場に常駐することでトラブルを低減でき、パフォーマンスを維持しました。
7.IT関連項目:全体のコスト削減に効果があった
- セキュリティの最適化・運用方法改善を実施
- IT(機器)・ネットワーク更改を実施
- 通信費・通信設備の更改を実施
クレジットコンサルティングに関するお問い合わせは下記までお願いいたします。
担当:久保田 伸
TEL: 03-3407-0283
kubota@icube-inc.co.jp